#働く女性と生理──“ふつうに話せる社会”を目指して
- CATEGORY
- Insights
- DATE

働く女性の生理事情 同じ女性でも違う理解や考え方
「痛みや不調で集中できない」
「椅子や服に血がついてしまった」
生理期間中も仕事は待ってくれません。
痛みやだるさに悩まされながらも、なんとか業務をこなす──そんな経験がある人は少なくないはずです。
Bé-A〈ベア〉が、2025年の国際女性デーに合わせて行ったアンケート調査では、約9割の女性が「生理によって仕事に支障がある」と回答しました。
痛みや眠気、集中力の低下といった症状により、普段通りにパフォーマンスを発揮できない人が多いことがわかります。
では、女性はこうした不調にどうやって対処をしているのでしょうか?
同じ調査では、薬を飲んだり、温めるなどして不調を和らげようとする一方で、「不調はあっても我慢する」と答えた方が約半数。
多くの女性が「仕方ない」と言葉にせず、誰にも言えないまま日々を過ごしているのが現状です。
そして「職場で生理に関して言いづらい、相談しにくいと感じている」人も、約6割。
生理にまつわる話題は、いまだにタブー視される場面も多く、職場での理解や配慮が進みにくい要因となっています。
また、生理の症状は人によって大きく異なるため、「我慢できる人」と「そうでない人」の間に無意識の分断が生まれてしまうこともあります。
「病気じゃない」
「精神が弱いから」
「みんな我慢してる」
これらは同アンケートに寄せられた、同じ女性からかけられた言葉たち。
「生理くらいで」といった偏見や無理解は、当事者にとって大きなプレッシャーとなり、心身の負担をさらに増やしてしまいます。
日本には「生理休暇制度」があるものの、実際に取得している人はごくわずか。休めても無給のところが多く、「男性上司に説明しづらいから」「利用している人が少ないから」といった理由で制度があっても、実際には使いづらいのが現実。このギャップは、解決していくべき課題のひとつと言えるでしょう。
生理は誰にとっても自然で大切な健康の一部、あたり前のこととして受け止める・話し合える環境にしていくことが大切です。
働く女性がもっと自分らしく力を発揮できる環境へ、どのような行動が必要だと考えますか?
#働く女性と生理 で、皆さんの考えを聞かせてください。
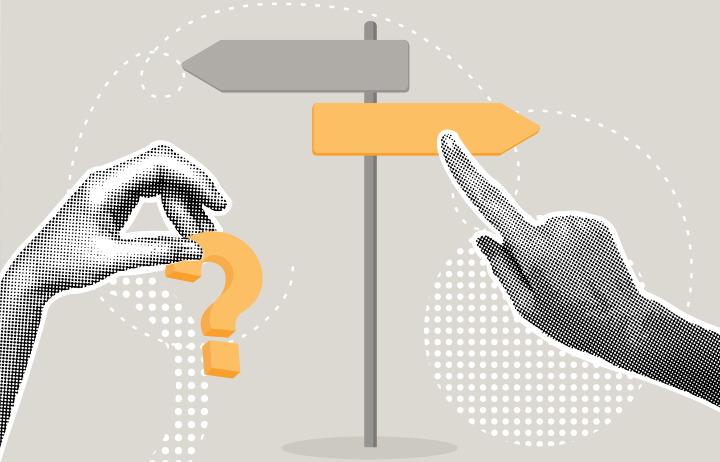
職場が変われば、働き方も変わる
働く女性の約9割が、生理によって仕事に支障を感じている。
Bé-A〈ベア〉が行ったアンケート調査では、このような結果が得られました。
この結果は、多くの方にとって共感と同時に「やっぱり」という感覚だったのではないでしょうか。
2020年度の厚労省の調査によると、女性労働者のうち、生理休暇を請求した割合は、0.3%*。
そして生理休暇を利用しにくい理由として、一番に上がるのは「男性上司に申請しにくい」というもの。ついで、「利用している人が少ないので申請しにくい」「休んで迷惑をかけたくない」という理由が上がります*。
この数値から見ても、実際、生理休暇制度の「使いにくさ」の現状がわかります。
一方で、独自のアプローチを始めている企業も。たとえば日本でも以下のような取組が進められています。
◆生理休暇を有給に
2019年から制度を改め、生理休暇を有給で取得できるようにした企業も。休暇の申請も総務の女性部長に社内LINEで申請するだけで良いように配慮されています。
◆生理前の不調であるPMSでも生理休暇を取得可能に
生理だけでなく生理前の不調であるPMSや不妊治療のための休暇についても男女共に取得できるようにした企業も。それぞれ名称をエフ休暇、ライフサポート休暇とし、名称からくる視覚的ストレス軽減により取得申請をしやすくするために工夫されています。
◆名前の変更で取得しやすく
生理休暇という名前をなくし、健康休暇に1本化。健康診断やワクチン 接種、つわり、更年期不調、不妊治療など取得できる範囲も拡大し、より多様なニーズに対応しています。
形骸化しがちな「生理休暇制度」を、より取得しやすく、柔軟にするための取り組みが進んでいます。
100人いれば100通りの生理がある。
誰もが同じように生理を経験するわけではなく、その時々の状態や職場環境によって、必要なサポートも異なるからこそ、「選択肢を増やす」ことが重要です。
働く人が自分の体と向き合いながら、必要なときに必要なケアを選べるようにすること。それこそが、多様な人が活躍できる組織の土台になるのではないでしょうか。
*2023年厚労省「働く女性と生理休暇について」資料より

性別問わず、誰もが生きやすい社会をめざして
生理と仕事をめぐる課題は、制度だけでなく、私たち一人ひとりの意識や行動にも深く関わっています。制度を整えることはもちろん大切。でも、それだけでは解決しない“空気”のような障壁が、今も多くの職場に残っているのではないでしょうか。
Bé-Aのアンケート調査では、このような意見が寄せられました。
Q.「女性が活躍できる社会」を作るためには、どのようなことが必要だと思いますか?(※複数回答可)
【1位】…生理・PMSへの理解
【2位】…女性が働きやすい職場設備づくり
【3位】…男性の理解
【4位】…相談しやすい職場環境づくり
まず大切なのは、「生理は特別なものではなく、健康に関わる自然な現象だ」という共通認識を持つことではないでしょうか。
話題にすること自体を避けるのではなく、日常的なこととして少しずつ会話に取り入れていくことで、安心して話せる空気が育まれます。
みんなが違う生理だからこそ、生理にまつわる体験や考えを共有し、理解を深め合うことが、より良い社会や職場環境の実現につながるのではないかとBé-A〈ベア〉は考えます。
性別問わず誰もが生きやすい社会を目指すために、今できることから始めましょう。
#働く女性と生理 アンケート結果へはこちらから
- TAGS
- 女性のエンパワーメント女性の健康生理